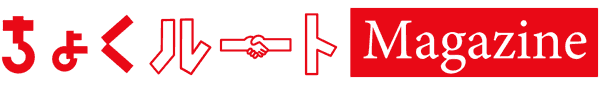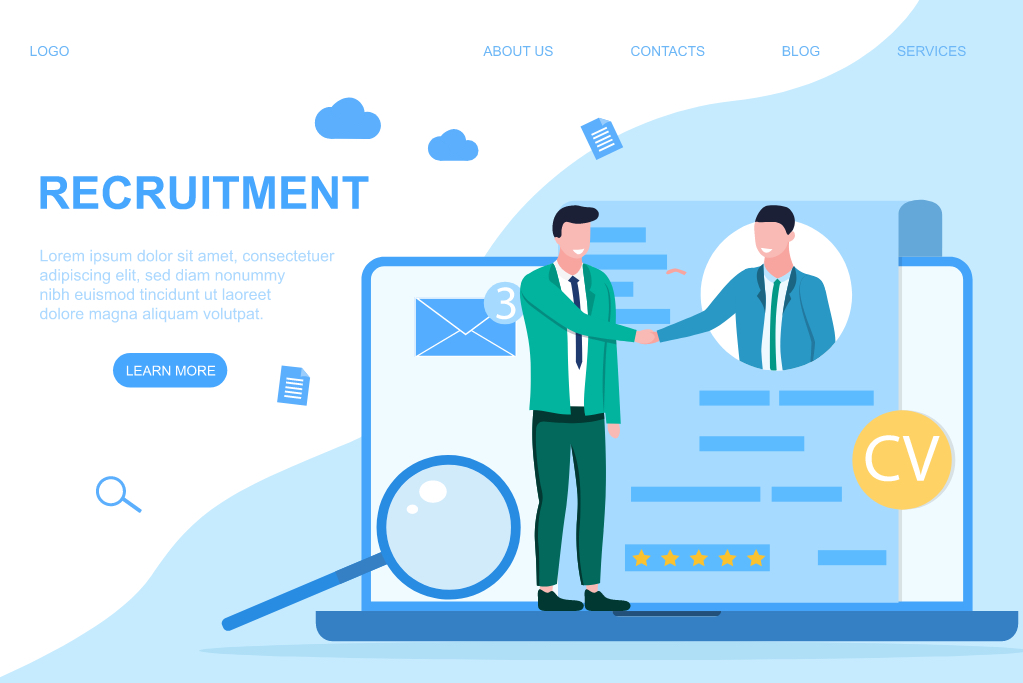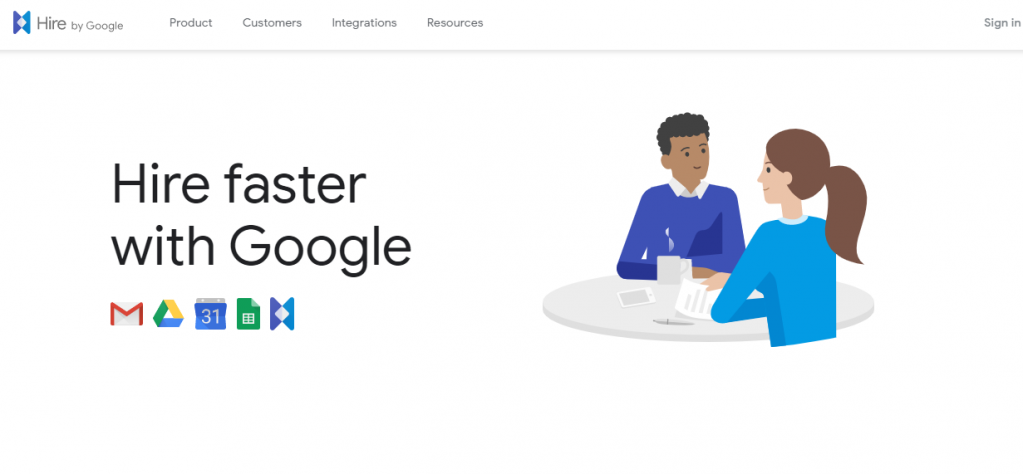2018/05/07
派遣会社が痛感する応募数の減少は「○○の設定」で解決できる

未経験者歓迎であっても、ターゲットを絞らない派遣求人は求職者には響かないため応募はされません。
そこで求人の魅力を伝えるペルソナを、派遣会社はどのように決めていくのか知ることが重要です。具体的なペルソナ設定方法を実践してみましょう。
そこで求人の魅力を伝えるペルソナを、派遣会社はどのように決めていくのか知ることが重要です。具体的なペルソナ設定方法を実践してみましょう。
なぜ自社の求人に応募するペルソナの設定が必要か

マーケティングの仕事をされている方なら、この「ペルソナ」という用語を頻繁に耳にされると思います。
ペルソナ(Personas)の語源は演劇で用いる「仮面」、マーケティング用語では「サービス・プロダクトにとって象徴的なユーザーモデルの意味で使われます。
年齢、性別、家族構成などの定量的な属性だけではなく、性格、価値観、生い立ち、趣味、なども定性的なデータも含めて、まるで実在するかのような人物像であり、分かりやすく表現すると、沢山存在する求職者の中で、派遣先に派遣すべき、最も大事な人物モデルのことをいいます。
「ペルソナ」を設定する理由はズバリ、『派遣案件を探している全ての求職者を獲得しようとしてはいけないし、そんなことができる訳がない。』という前提があるからです。
求人広告を作成する際、全ての求職者のニーズを満たそうとすると、どっちつかずの誰のニーズも満たさない求人広告が出来あがってしまいます。求職者に賛同してもらう求人広告を作るために重要なことは、1人の求職者ために作成することが重要で、その人は絶対に逃さないことです。
その手段として、「ペルソナ」を設定する必要があるのです。
派遣先との条件確認がペルソナ設定を左右する

まず派遣先から受注をしたら、受注内容の詳細を確認する必要があります。
ただ派遣事業をしていると、詳細を知らない仕事の受注を受けることもあますので、2つの要件を基準にしてヒアリングするクセをつけるといいでしょう。
① 必要条件(must / 資格を持ったスタッフでなければならない!or こんなスタッフは絶対ダメ!)
② 十分条件(want / 日勤も夜勤も働けるスタッフだったらいいな!)
ここで大事なことは、顧客の条件はコントロールしながら進めることです。オーダーする側は理想が高くなりすぎてしまいがちであるため、『そんな応募者、どこに存在するのですか???』ということになりかねないからです。
また、顧客のMUSTの多くはWANTです。
法律上語ることは微妙ではあるのですが、一般論として、未だに年齢設定をされるところもありますが、いい人物であれば受入れて頂けることが多いのも事実です。
WANTの要件は、就業後、実務経験や研修で補うことができることも多いと思いますので、そもそもWANTが必要なのかを議論するべきと思います。
とは言っても、業務の特性上、免許が必要なものもありますので、MUSTとWANTは慎重に分類して下さい。
結論としては、本当のMUSTとWANTを主導権を握り判断しながら、顧客と勤務してほしいスタッフ像について、情報共有を進めることが肝要だと考えます。
この際気を付けるべきは、その人の仕事上の能力だけでなく、性格や考え方も考慮したほうが良いということです。退職理由の多くは、職場の人間関係が上手くいかなかったり、仕事内容が合わなかったりすることが多いため、無駄に退職率を上げてしまった経験があります。
例えば、コツコツ仕事をすることが得意な人に、タクトタイムの早い作業をしてもらうと、仕事の継続に問題が出てしまいますね。
ただ派遣事業をしていると、詳細を知らない仕事の受注を受けることもあますので、2つの要件を基準にしてヒアリングするクセをつけるといいでしょう。
① 必要条件(must / 資格を持ったスタッフでなければならない!or こんなスタッフは絶対ダメ!)
② 十分条件(want / 日勤も夜勤も働けるスタッフだったらいいな!)
ここで大事なことは、顧客の条件はコントロールしながら進めることです。オーダーする側は理想が高くなりすぎてしまいがちであるため、『そんな応募者、どこに存在するのですか???』ということになりかねないからです。
また、顧客のMUSTの多くはWANTです。
法律上語ることは微妙ではあるのですが、一般論として、未だに年齢設定をされるところもありますが、いい人物であれば受入れて頂けることが多いのも事実です。
WANTの要件は、就業後、実務経験や研修で補うことができることも多いと思いますので、そもそもWANTが必要なのかを議論するべきと思います。
とは言っても、業務の特性上、免許が必要なものもありますので、MUSTとWANTは慎重に分類して下さい。
結論としては、本当のMUSTとWANTを主導権を握り判断しながら、顧客と勤務してほしいスタッフ像について、情報共有を進めることが肝要だと考えます。
この際気を付けるべきは、その人の仕事上の能力だけでなく、性格や考え方も考慮したほうが良いということです。退職理由の多くは、職場の人間関係が上手くいかなかったり、仕事内容が合わなかったりすることが多いため、無駄に退職率を上げてしまった経験があります。
例えば、コツコツ仕事をすることが得意な人に、タクトタイムの早い作業をしてもらうと、仕事の継続に問題が出てしまいますね。
また、派遣先と協議した要件に応じて、派遣料金の交渉をしておくべきです。
「前回と同じ条件でいきましょう!」と気前の良いことを言ってしまうと、せっかくの料金交渉をしやすい絶好の機会を逃してしまいます。
「前回と同じ条件でいきましょう!」と気前の良いことを言ってしまうと、せっかくの料金交渉をしやすい絶好の機会を逃してしまいます。
やってはいけない!ペルソナのでっち上げ

派遣先(顧客)の意見聴取ができれば、早速ペルソナの設定を進めていきましょう!
しかし、ペルソナのでっち上げはダメです。ペルソナは実際の求職者をベースに設定するものです。勝手に自分の思う通りにでっち上げると、理想ばかりの存在しないペルソナしかできなくなってしまいます。
求職者のタイプは様々ですが、それを分析していくことで共通点を見つけパターン化することができます。
定性データを分析していくと、行動、思考、生活のパターンが見えてきます。一般的には、同じ質問を10人にした場合、回答パターンは4~5パターンに収束されます。(だから、アンケート調査が成立しますね。)
ペルソナのベースは「人」ではありません。ユーザーデータから分析したパターンを仮設定し、実際にインタビューをして得られた事実を肉付けし作り上げます。
しかし、ペルソナのでっち上げはダメです。ペルソナは実際の求職者をベースに設定するものです。勝手に自分の思う通りにでっち上げると、理想ばかりの存在しないペルソナしかできなくなってしまいます。
求職者のタイプは様々ですが、それを分析していくことで共通点を見つけパターン化することができます。
定性データを分析していくと、行動、思考、生活のパターンが見えてきます。一般的には、同じ質問を10人にした場合、回答パターンは4~5パターンに収束されます。(だから、アンケート調査が成立しますね。)
ペルソナのベースは「人」ではありません。ユーザーデータから分析したパターンを仮設定し、実際にインタビューをして得られた事実を肉付けし作り上げます。
ペルソナは自社の派遣スタッフを基軸に考えるのがベスト

派遣事業者のスタッフ管理担当の方は、今まで多くの派遣社員とコミュニケーションを取ってきたと思います。その中には、就業意識の高いスタッフ、遅刻が多いスタッフ、顧客社員より仕事ができるスタッフなどなど、多くのタイプの派遣社員とお付き合いをされてきたと思います。
社歴にもよりますが、中小中堅規模でも、数千人規模のサンプルをお持ちではないでしょうか?
受注した派遣先の仕事や環境に応じて、ご自分の知っている派遣スタッフの中から、彼や彼女ならピッタリ合うかもと思えるスタッフを5名前後ピックアップしましょう。
可能であれば、ペルソナ候補にピックアップしたスタッフにインタビューをしてください。
その方が、分析確度が向上するからです。
インタビューの内容は、5項目を確認するのがいいと思います。以下の5つが明確であれば、ペルソナを作るための言語化をしやすくなるからです。
ⅰ)仕事に係わること
どうしてこの仕事に応募したか?、実際に今どんな仕事をしているのか?、
今の仕事の好きなところ、今の仕事の辛いところ、職務遂行の知識習得方法、評価のされ方
ⅱ)環境に係わること派遣先と自社の魅力や欠点
ⅲ)人に係わること
指揮命令者や派遣先社員との関係、派遣社員同士の関係、尊敬できる同僚・上役の有無、職場の雰囲気
ⅳ)個人のこと(事前に調べることも可能)
年齢、性別、住所、通勤方法、一人暮らしか否か、勤務時間数の実態、
職業観・倫理観(仕事に対する姿勢や大事にしていること)、ワークライフバランスへの考え方、家族の評価、将来の夢・目標
ⅴ)その他入社前と今とのギャップはないか?
もしインタビューができなくても、派遣スタッフのデータベースは存在している可能性は考えられます。ひょっとするとスタッフ管理担当者の頭の中にデータベース化されているかもしれませんので、できる限り具体的に言語化してください。
社歴にもよりますが、中小中堅規模でも、数千人規模のサンプルをお持ちではないでしょうか?
受注した派遣先の仕事や環境に応じて、ご自分の知っている派遣スタッフの中から、彼や彼女ならピッタリ合うかもと思えるスタッフを5名前後ピックアップしましょう。
可能であれば、ペルソナ候補にピックアップしたスタッフにインタビューをしてください。
その方が、分析確度が向上するからです。
インタビューの内容は、5項目を確認するのがいいと思います。以下の5つが明確であれば、ペルソナを作るための言語化をしやすくなるからです。
ⅰ)仕事に係わること
どうしてこの仕事に応募したか?、実際に今どんな仕事をしているのか?、
今の仕事の好きなところ、今の仕事の辛いところ、職務遂行の知識習得方法、評価のされ方
ⅱ)環境に係わること派遣先と自社の魅力や欠点
ⅲ)人に係わること
指揮命令者や派遣先社員との関係、派遣社員同士の関係、尊敬できる同僚・上役の有無、職場の雰囲気
ⅳ)個人のこと(事前に調べることも可能)
年齢、性別、住所、通勤方法、一人暮らしか否か、勤務時間数の実態、
職業観・倫理観(仕事に対する姿勢や大事にしていること)、ワークライフバランスへの考え方、家族の評価、将来の夢・目標
ⅴ)その他入社前と今とのギャップはないか?
もしインタビューができなくても、派遣スタッフのデータベースは存在している可能性は考えられます。ひょっとするとスタッフ管理担当者の頭の中にデータベース化されているかもしれませんので、できる限り具体的に言語化してください。
派遣スタッフからのヒアリング内容を元に人物像を設定する

ピックアップしたスタッフへのヒアリングした内容を、整理し言語化していきましょう。
その方法として、
① MUST(必要条件)とWANT(十分要件)を再設定した上で
② インタビューをした下記5つの項目に立ち戻って、共通点を見つけて下さい。
共通点については、「1項目=聞き取り人数÷2程度」でイイと思います。
ⅰ)仕事に係わること
ⅱ)環境に係わること
ⅲ)人に係わること
ⅳ)スタッフ個人のこと(事前に調べることも可能)
以上がペルソナの人物像を設定する流れとなります。
ペルソナができたとしても、採用市場にそのペルソナに合う人材がいなければ意味がありません。
よってペルソナを決定することをゴールにするのではなく、採用市場に求める人物像がいるのか、実際に広告にペルソナを反映させ、PDCAを廻し、検証することが重要になります。
その方法として、
① MUST(必要条件)とWANT(十分要件)を再設定した上で
② インタビューをした下記5つの項目に立ち戻って、共通点を見つけて下さい。
共通点については、「1項目=聞き取り人数÷2程度」でイイと思います。
ⅰ)仕事に係わること
ⅱ)環境に係わること
ⅲ)人に係わること
ⅳ)スタッフ個人のこと(事前に調べることも可能)
以上がペルソナの人物像を設定する流れとなります。
ペルソナができたとしても、採用市場にそのペルソナに合う人材がいなければ意味がありません。
よってペルソナを決定することをゴールにするのではなく、採用市場に求める人物像がいるのか、実際に広告にペルソナを反映させ、PDCAを廻し、検証することが重要になります。
求人広告について、建物で言えば土台にあたる、「誰に伝えるか?」がうまくいかないと、採用が上手くいきません。なぜなら、具体性のない曖昧な情報では、入社後の自分をイメージできないため、興味を持ってもらえず、その結果求職者に安心をしてもらえないため、応募数そのものが減少してしまうからです。
仮に面接まで到達したとしても、求める人物像が明確でないと、派遣先に合ったスタッフか否かの見極めが面接者の判断次第になり、安定したお客様への貢献が難しくなります。
ペルソナ設定は「誰に伝えるか?」を決めること、派遣会社の採用を成功させるためのポイントなので、実践を通じて理解していきましょう。
仮に面接まで到達したとしても、求める人物像が明確でないと、派遣先に合ったスタッフか否かの見極めが面接者の判断次第になり、安定したお客様への貢献が難しくなります。
ペルソナ設定は「誰に伝えるか?」を決めること、派遣会社の採用を成功させるためのポイントなので、実践を通じて理解していきましょう。
 ちょくマガ編集部 濱上真輔
ちょくマガ編集部 濱上真輔
食品メーカーにて株式管理、東証2部への移行、会社合併業務などを担当したのち、製造請負・派遣会社に転職し新規株式上場、ミッション制定、人事・評価制度の構築と運営などに携わる。
製造請負・派遣の業界団体を一から立ち上げ、労働者派遣法改正、製造請負マニュアル刊行、労働組合のナショナルセンター・連合との協議、東日本大震災復興支援事業の立ち上げを主管。
大阪に本社を置く人材派遣会社で派遣事業部長を経たのち、株式会社アドヴァンテージに入社。現在では業界の垣根を超え、企業の採用支援や、商工会議所等の講演に従事している。
製造請負・派遣の業界団体を一から立ち上げ、労働者派遣法改正、製造請負マニュアル刊行、労働組合のナショナルセンター・連合との協議、東日本大震災復興支援事業の立ち上げを主管。
大阪に本社を置く人材派遣会社で派遣事業部長を経たのち、株式会社アドヴァンテージに入社。現在では業界の垣根を超え、企業の採用支援や、商工会議所等の講演に従事している。
関連記事
ちょくルートMagazineについて
ちょくルートMagazineは、経営戦略は「人」であると考える経営者、人事担当者向けに人材不足の問題を解消すべく、採用に関するニュースや求職者動向、成功事例を発信するメディアです。特に、自社採用サイトを活用した採用手法をお届けしています。