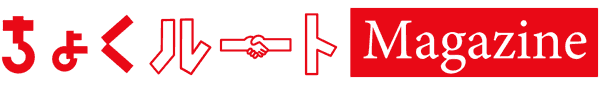2018/07/24
愛のギロチン ~Part1「退職の決断」

求人広告の代理店で働く「俺」は退職を決意するも、久々に会った後輩に慰めを受け、惨めな想いをしてしまう。
「先輩はクライアントにどんな価値を提供できるんですか」
採用コンサルティングビジネスで成功する後輩に言われた言葉が胸に引っかかりながら、帰宅。
やけ酒の帰りに会った一人の老人との出会いが、「俺」の人生を変えていく。
「先輩はクライアントにどんな価値を提供できるんですか」
採用コンサルティングビジネスで成功する後輩に言われた言葉が胸に引っかかりながら、帰宅。
やけ酒の帰りに会った一人の老人との出会いが、「俺」の人生を変えていく。
短編小説 愛のギロチン(全3回)

「え? 辞めるんですか、会社」
錦糸町南口の小奇麗な居酒屋。俺が退職前の有給消化中だと知った本木は、驚いた顔をして言った。
「ああ、まだ引き継ぎで何度かは出社するけどな」
「……次、どうするんです?」
予想された質問に、落ち着いた口調を意識して言った。
「まあ、ゆっくり考えようかと思ってな。いい会社が見つかるまでは、フリーランスとして活動するつもりだ」
「フリーランス? 先輩が?」
本木は2年前まで同じ会社で働いていた後輩だ。
年齢は今年40の俺より3つ4つ下だが、優秀な営業マンだった。周りの留意も気にせずあっさり退職し、やがて自分で会社を立ち上げた。
採用コンサルティングの事業で成功し、組織もどんどん大きくなっているらしい。
たまたま音楽の趣味が合ったことがキッカケで話すようになり、会社を辞めた後も、こうして半年に一度くらいの頻度で飲みに行く。
「フリーランスか……うーん」
本木はそう言って難しそうな顔をする。
先日誘いの電話を受けたとき、「じゃあウチに来てくださいよ」と言われることを期待しなかったといえば嘘になる。
「……なんだよ、問題でもあるのか」
「いや……ていうか、そもそもなんで辞めるんですか」
「なんでって……」
優秀な本木と違って俺は、ごく平凡な営業マンだ。
入社して15年以上、過去には社内の営業マンランキングで上位にいたこともあるが、だいたいの成績は中の上。
それなりの売上は立てられるが、どちらかと言えば暗い性格で人望もないので、マネージャーへの昇進は叶わなかった。
なぜ辞めるのか。正直に言えば、明確な理由などない。
強いて言うなら、居心地が悪くなったのだ。
リーマンショック以降、業界全体のデフレが顕著になってきたこともあって、俺たちのような「中途半端な年代の社員」に対する風当たりは強くなっていた。
年々の昇給が重なって給与は高いくせに、若手と比べて売上が劇的に高いわけでもない。
そういう存在を会社が疎ましく思うのもわかる。
「そろそろ辞めてくれないかな」という空気のなか、平然と40歳を迎えられるほど俺は図太くない。コミュニケーション能力はないくせに、人の顔色には敏感な性格なのだ。
「俺も来年40だし、このままずっと会社にいてもな」
本木の視線を避けるように箸を取り、乾きかけたお新香を口に運んだ。
「確かにそれくらいで独立する人は多いですけどね。でもなあ……」
……なんだ、その言い方。なぜ素直に応援してくれない。
「でも……なんだよ」
「いいですか、先輩。独立したら、自分で稼がなきゃならないんですよ。週5日8時間働いていたからってお給料がもらえるわけじゃない」
「……そんなことわかってるよ」
「先輩、今は価値社会ですよ。価値を提供して、その対価としてお金をもらう。大企業の商品だからって売れるって時代は終わりつつあります」
何の話だ。価値社会? 対価として金をもらう?
本木はそして、俺のことをじっと見つめた。
「先輩だからハッキリ言わせてもらいますが、先輩はクライアントに、いったいどんな価値を提供できるんです?」
錦糸町南口の小奇麗な居酒屋。俺が退職前の有給消化中だと知った本木は、驚いた顔をして言った。
「ああ、まだ引き継ぎで何度かは出社するけどな」
「……次、どうするんです?」
予想された質問に、落ち着いた口調を意識して言った。
「まあ、ゆっくり考えようかと思ってな。いい会社が見つかるまでは、フリーランスとして活動するつもりだ」
「フリーランス? 先輩が?」
本木は2年前まで同じ会社で働いていた後輩だ。
年齢は今年40の俺より3つ4つ下だが、優秀な営業マンだった。周りの留意も気にせずあっさり退職し、やがて自分で会社を立ち上げた。
採用コンサルティングの事業で成功し、組織もどんどん大きくなっているらしい。
たまたま音楽の趣味が合ったことがキッカケで話すようになり、会社を辞めた後も、こうして半年に一度くらいの頻度で飲みに行く。
「フリーランスか……うーん」
本木はそう言って難しそうな顔をする。
先日誘いの電話を受けたとき、「じゃあウチに来てくださいよ」と言われることを期待しなかったといえば嘘になる。
「……なんだよ、問題でもあるのか」
「いや……ていうか、そもそもなんで辞めるんですか」
「なんでって……」
優秀な本木と違って俺は、ごく平凡な営業マンだ。
入社して15年以上、過去には社内の営業マンランキングで上位にいたこともあるが、だいたいの成績は中の上。
それなりの売上は立てられるが、どちらかと言えば暗い性格で人望もないので、マネージャーへの昇進は叶わなかった。
なぜ辞めるのか。正直に言えば、明確な理由などない。
強いて言うなら、居心地が悪くなったのだ。
リーマンショック以降、業界全体のデフレが顕著になってきたこともあって、俺たちのような「中途半端な年代の社員」に対する風当たりは強くなっていた。
年々の昇給が重なって給与は高いくせに、若手と比べて売上が劇的に高いわけでもない。
そういう存在を会社が疎ましく思うのもわかる。
「そろそろ辞めてくれないかな」という空気のなか、平然と40歳を迎えられるほど俺は図太くない。コミュニケーション能力はないくせに、人の顔色には敏感な性格なのだ。
「俺も来年40だし、このままずっと会社にいてもな」
本木の視線を避けるように箸を取り、乾きかけたお新香を口に運んだ。
「確かにそれくらいで独立する人は多いですけどね。でもなあ……」
……なんだ、その言い方。なぜ素直に応援してくれない。
「でも……なんだよ」
「いいですか、先輩。独立したら、自分で稼がなきゃならないんですよ。週5日8時間働いていたからってお給料がもらえるわけじゃない」
「……そんなことわかってるよ」
「先輩、今は価値社会ですよ。価値を提供して、その対価としてお金をもらう。大企業の商品だからって売れるって時代は終わりつつあります」
何の話だ。価値社会? 対価として金をもらう?
本木はそして、俺のことをじっと見つめた。
「先輩だからハッキリ言わせてもらいますが、先輩はクライアントに、いったいどんな価値を提供できるんです?」

自宅があるのは千葉市稲毛区だ。
錦糸町から総武線快速で稲毛駅まで来て、そこから小仲台方面に徒歩10分ほどにあるアパートに部屋を借りている。
本木とは何となく気まずいまま別れた。
本木は本木で真剣に心配してくれていたのだろうし、同情的な慰めももらったが、「ウチに来てください」という言葉はついに出なかった。
帰り道のいつものコンビニエンスストアに、惰性で入る。
自動ドアをくぐり、頭痛に似た酔いを覚えつつ、それでも酒売り場の前に立った。
別段酒が好きなわけではないが、このまま寝られる気もしなかった。
冷蔵庫の中にはギッシリと酒の缶が並んでいる。
俺の隣で、今から一緒に飲むのだろう、若いカップルが一緒につまみを買い込んでいる。
女は細くてスタイルが良かった。どう見ても男物のシャツに部屋着風の短パンを履いている。
一方男は170センチで小太りの俺とはまるで違う、背が高く喧嘩も強そうなイケメンだ。
最近流行りの、アルコール度数の高いチューハイを4本買って店を出た。
何か、思い切り叫びたい気分だった。5月の晴れた夜。
だが、俺の心はドロドロした雲で覆われている。
家の方向へ歩き出しながら1本目を開ける。
喉に流し込んだが、ただ刺激があるだけで、うまくもなんともない。
裏道に一本入れば、月以外の明るさはなかった。
その薄暗さが、自分の人生を表している気がした。特別な才能もなければ、恋人もいない、人生の目標すらない。そして俺は今、会社まで辞めようとしているのだ。
「クソ……」
思わず悪態をついた。その声すら弱々しくて、あまりの情けなさに笑いそうになる。
2階建てのアパートは、壁が薄いと有名なウィークリーマンションに毛が生えた程度のものだ。
三角屋根の四角い建物に、階段が外付けされている。
部屋数は12。1階に6戸、2階に6戸、俺の部屋は2階の一番奥だ。
運動不足のせいか、酔いのせいか、あるいは精神的なダメージのせいか、体が重くて階段を登るのに苦労した。
まるで体の中を血ではなくヘドロが流れているような気分。
手すりを掴んで一歩一歩ゆっくり上がっていくと、どこからか声が聞こえた。
錦糸町から総武線快速で稲毛駅まで来て、そこから小仲台方面に徒歩10分ほどにあるアパートに部屋を借りている。
本木とは何となく気まずいまま別れた。
本木は本木で真剣に心配してくれていたのだろうし、同情的な慰めももらったが、「ウチに来てください」という言葉はついに出なかった。
帰り道のいつものコンビニエンスストアに、惰性で入る。
自動ドアをくぐり、頭痛に似た酔いを覚えつつ、それでも酒売り場の前に立った。
別段酒が好きなわけではないが、このまま寝られる気もしなかった。
冷蔵庫の中にはギッシリと酒の缶が並んでいる。
俺の隣で、今から一緒に飲むのだろう、若いカップルが一緒につまみを買い込んでいる。
女は細くてスタイルが良かった。どう見ても男物のシャツに部屋着風の短パンを履いている。
一方男は170センチで小太りの俺とはまるで違う、背が高く喧嘩も強そうなイケメンだ。
最近流行りの、アルコール度数の高いチューハイを4本買って店を出た。
何か、思い切り叫びたい気分だった。5月の晴れた夜。
だが、俺の心はドロドロした雲で覆われている。
家の方向へ歩き出しながら1本目を開ける。
喉に流し込んだが、ただ刺激があるだけで、うまくもなんともない。
裏道に一本入れば、月以外の明るさはなかった。
その薄暗さが、自分の人生を表している気がした。特別な才能もなければ、恋人もいない、人生の目標すらない。そして俺は今、会社まで辞めようとしているのだ。
「クソ……」
思わず悪態をついた。その声すら弱々しくて、あまりの情けなさに笑いそうになる。
2階建てのアパートは、壁が薄いと有名なウィークリーマンションに毛が生えた程度のものだ。
三角屋根の四角い建物に、階段が外付けされている。
部屋数は12。1階に6戸、2階に6戸、俺の部屋は2階の一番奥だ。
運動不足のせいか、酔いのせいか、あるいは精神的なダメージのせいか、体が重くて階段を登るのに苦労した。
まるで体の中を血ではなくヘドロが流れているような気分。
手すりを掴んで一歩一歩ゆっくり上がっていくと、どこからか声が聞こえた。

「おい、あんた」
空耳かとも思ったが、「おい」と再度呼ばれて、足を止めた。
「こっちだ、こっち」
声は階段の下、いや、道路の方からしている。
振り返ってそちらを見ると、マンションに接している細い道路、そこに置かれた自動販売機の前に、誰かが座っているのが見えた。
自動販売機の発する白い光の中に、頭の白い老人が浮かび上がっている。
「……」
状況が飲み込めず俺は黙って見ていた。
「そう、あんた。あんただよ」
老人はそう言って俺を指さした。やはり俺に言っているらしい。
一体なんだ? 酔っぱらいか、あるいは、痴呆老人か。
「ちょっと、こっち来てくんねえか」
無視しようかとも思った。いや、普通ならそうするべきだろう。
もしかしたら幽霊のたぐいかもしれない。
………だが、残念ながら俺はこういう状況に弱いのだ。強いられたらどうしても断れない。
この性格のせいで上司にもクライアントにも随分無理をさせられてきた。
年齢を経ようが会社を辞めようが、この性格は簡単にはかわらない。
仕方なく上ってきた階段を降り、集合ポストの前をぐるりと回り、老人のいる場所まで行った。
「……なんですか」
自販機の強い光に目を細めつつ聞くと、「動けねえんだ」と老人は答えた。
「……動けない?」
「そこでコケたんだよ。ちょっと足を痛めて……歩けねえことはねえが、階段はちょっとな」
そう言って老人は、俺がさっき上っていた階段を指さした。
言葉はハッキリしている。頭は真っ白だが、ヨボヨボという感じはしない。
あらためてその顔を見つめて、俺は「あっ」と声を出した。
「……もしかして」
俺はそこでやっと、老人が同じアパートの住人だと気付いた。
確か、2階の一番手前の部屋だ。過去に数度、その姿を見かけたことがあった。
「そうだよ。あんたと同じ階に住んでるもんだ。つうわけで、ちょっと肩貸してくれや」
「……はあ」
言われるまま老人に肩を貸し、立ち上がらせた。
小柄だが痩せているわけではなく、肌が黒く活動的な感じだ。
年齢は60代後半くらいだろうか。一緒に歩き始めると老人は一度だけうっと呻いたが、そこからは何とか歩き出す。
「……大丈夫ですか。病院行ったほうがいいんじゃないですか」
「こんな時間に病院がやってるかよ、阿呆」
……クチの悪い爺さんだ。善意で助けてくれている相手を阿呆呼ばわりとは。
そして俺と老人は一歩一歩、ゆっくりと階段を上った。
2階の一番手前の扉の前まで来ると、「ここだ、俺んち」と老人は言う。表札には「大貫」とある。
「……じゃ、私はこれで」
そう言い残して廊下を歩きだすと、後ろから「おい、あんちゃん」と声がかかる。
「なんですか」
「あんた、名前は?」
「……崎野です」
「仕事は何曜休みだ」
「は?」
いったい何なのだ、この爺さん。どうしてそんなことを言わなきゃならない。
近所付き合いなどまっぴらだ。そもそも俺は今日、気分が悪い。頼むから放っておいてくれ。
「な、仕事してるんだろ? 休みはいつだ」
うるさいな、と思う。いま一番聞かれたくない話だ。
転職先も決まっていないのに退職だけは決まっているのだ。
だが、苛立ちよりも、情けなさの方が勝った。そんな自分が恥ずかしくてたまらない。
「土日休みですよ、普通に」
ムキになって言った。別に嘘は言っていない。
有給消化中ではあるが、ウチの会社は平日勤務で土日休みなのだ。
俺の返事を聞いて大貫老人はなぜかニヤリと笑った。
「てこたあ、明日は休みってことだ」
「……は?」
「じゃあな」
大貫はそれ以上は何も言わず、慣れた手付きで扉を開け、部屋の中に消えた。
空耳かとも思ったが、「おい」と再度呼ばれて、足を止めた。
「こっちだ、こっち」
声は階段の下、いや、道路の方からしている。
振り返ってそちらを見ると、マンションに接している細い道路、そこに置かれた自動販売機の前に、誰かが座っているのが見えた。
自動販売機の発する白い光の中に、頭の白い老人が浮かび上がっている。
「……」
状況が飲み込めず俺は黙って見ていた。
「そう、あんた。あんただよ」
老人はそう言って俺を指さした。やはり俺に言っているらしい。
一体なんだ? 酔っぱらいか、あるいは、痴呆老人か。
「ちょっと、こっち来てくんねえか」
無視しようかとも思った。いや、普通ならそうするべきだろう。
もしかしたら幽霊のたぐいかもしれない。
………だが、残念ながら俺はこういう状況に弱いのだ。強いられたらどうしても断れない。
この性格のせいで上司にもクライアントにも随分無理をさせられてきた。
年齢を経ようが会社を辞めようが、この性格は簡単にはかわらない。
仕方なく上ってきた階段を降り、集合ポストの前をぐるりと回り、老人のいる場所まで行った。
「……なんですか」
自販機の強い光に目を細めつつ聞くと、「動けねえんだ」と老人は答えた。
「……動けない?」
「そこでコケたんだよ。ちょっと足を痛めて……歩けねえことはねえが、階段はちょっとな」
そう言って老人は、俺がさっき上っていた階段を指さした。
言葉はハッキリしている。頭は真っ白だが、ヨボヨボという感じはしない。
あらためてその顔を見つめて、俺は「あっ」と声を出した。
「……もしかして」
俺はそこでやっと、老人が同じアパートの住人だと気付いた。
確か、2階の一番手前の部屋だ。過去に数度、その姿を見かけたことがあった。
「そうだよ。あんたと同じ階に住んでるもんだ。つうわけで、ちょっと肩貸してくれや」
「……はあ」
言われるまま老人に肩を貸し、立ち上がらせた。
小柄だが痩せているわけではなく、肌が黒く活動的な感じだ。
年齢は60代後半くらいだろうか。一緒に歩き始めると老人は一度だけうっと呻いたが、そこからは何とか歩き出す。
「……大丈夫ですか。病院行ったほうがいいんじゃないですか」
「こんな時間に病院がやってるかよ、阿呆」
……クチの悪い爺さんだ。善意で助けてくれている相手を阿呆呼ばわりとは。
そして俺と老人は一歩一歩、ゆっくりと階段を上った。
2階の一番手前の扉の前まで来ると、「ここだ、俺んち」と老人は言う。表札には「大貫」とある。
「……じゃ、私はこれで」
そう言い残して廊下を歩きだすと、後ろから「おい、あんちゃん」と声がかかる。
「なんですか」
「あんた、名前は?」
「……崎野です」
「仕事は何曜休みだ」
「は?」
いったい何なのだ、この爺さん。どうしてそんなことを言わなきゃならない。
近所付き合いなどまっぴらだ。そもそも俺は今日、気分が悪い。頼むから放っておいてくれ。
「な、仕事してるんだろ? 休みはいつだ」
うるさいな、と思う。いま一番聞かれたくない話だ。
転職先も決まっていないのに退職だけは決まっているのだ。
だが、苛立ちよりも、情けなさの方が勝った。そんな自分が恥ずかしくてたまらない。
「土日休みですよ、普通に」
ムキになって言った。別に嘘は言っていない。
有給消化中ではあるが、ウチの会社は平日勤務で土日休みなのだ。
俺の返事を聞いて大貫老人はなぜかニヤリと笑った。
「てこたあ、明日は休みってことだ」
「……は?」
「じゃあな」
大貫はそれ以上は何も言わず、慣れた手付きで扉を開け、部屋の中に消えた。

次の日の朝、俺は耳障りなノックの音で目を覚ました。
目を薄っすらと開くと、ベッド脇のローテーブルの上に、昨日買ったチューハイの空き缶が並べて置いてあった。
あまり覚えていないが、結局全部飲んでしまったらしい。
元来あまり酒には強くない。だが、飲まずにはいられなかったのだろう。
ノックの音は続いている。頭がガンガンした。
「……もう、なんだよ」
家を訪ねてくる人間に心当たりはなかった。通販で何かを買った覚えもない。
このご時世に、訪問販売でもないだろう。
だが、どうしても馬鹿正直な俺はこういうものを無視できない。
ほとほと自分の性格が嫌になる。全身の怠さを覚えながらベッドから出て、玄関の前に立った。
「どちらさまですか?」
扉の外に向かって言った。そこにいる人間は何かを言ったようだったが、よく聞こえない。
安アパートのせいで扉にのぞき穴もなく、面倒になって扉を開けた。
「あっ、どうも」
立っていたのは見慣れぬ中年男性だった。
紺色のスーツ……いや、ブレザーのようなものを着て、なぜか白い手袋をつけている。
手には角ばった帽子。
一瞬、警察官かと思ったが、そういう雰囲気でもない。
なんだ、誰なんだ。素性を聞こうと口を開きかけたとき、相手が言った。
「ああ、よかった。お留守かと思いました。もう私、困ってしまって」
「……あの、部屋、間違えてませんか?」
今更のように頭痛がしてくる。体を巡る血がドロドロしている。
二日酔いだ。早く中に戻って横になりたい。
「え? 崎野さんですよね」
「……え?」
「あの、私、タクシーの運転手です。大貫さんが下でお待ちです。すみませんけど、来てもらえますか」
「はい?」
いったい何を言っているのだ。
だが、大貫さん、という言葉が頭の何処かに引っかかる。
――大貫さん。そうだ。昨日の夜に確か――
「じゃあ、待ってますからね。あの人、ちょっと変ですよ、困ってるんですから」
そう言って運転手はそそくさと廊下を駆けていった。
着古したポロシャツにしわだらけのチノパン、ボサボサの髪。
まったく自分が嫌になる。なぜこんな理不尽につきあおうとしているのか。
いきなりやってきたタクシー運転手など、無視してしまえばいいではないか。
だが俺はそれができない。
洗面所で手を濡らし、即席の寝癖直しをして、一応サイフと携帯を持ち、部屋を出る。
廊下を進み、階段を降り始めると、確かに一台のタクシーが停車しているのが見えた。
5月の朝8時である。
天気もよく、気持ちの良い春の朝なのだろうが、二日酔いとこの妙な状況のせいですこぶる気分が悪い。
「なんなんだよ……」
誰に言うでもなく呟きながら、降りていく。
やがてタクシーの後部座席の窓が滑らかに開いた。
「やっと来たか。男のくせに準備が遅ぇよ」
大貫だった。確かに昨日の夜、自動販売機の前で会った老人だ。
助けてもらっているくせにひどく偉そうで、感謝の言葉ひとつもなく帰っていった、あのクチの悪い爺さん。
目を薄っすらと開くと、ベッド脇のローテーブルの上に、昨日買ったチューハイの空き缶が並べて置いてあった。
あまり覚えていないが、結局全部飲んでしまったらしい。
元来あまり酒には強くない。だが、飲まずにはいられなかったのだろう。
ノックの音は続いている。頭がガンガンした。
「……もう、なんだよ」
家を訪ねてくる人間に心当たりはなかった。通販で何かを買った覚えもない。
このご時世に、訪問販売でもないだろう。
だが、どうしても馬鹿正直な俺はこういうものを無視できない。
ほとほと自分の性格が嫌になる。全身の怠さを覚えながらベッドから出て、玄関の前に立った。
「どちらさまですか?」
扉の外に向かって言った。そこにいる人間は何かを言ったようだったが、よく聞こえない。
安アパートのせいで扉にのぞき穴もなく、面倒になって扉を開けた。
「あっ、どうも」
立っていたのは見慣れぬ中年男性だった。
紺色のスーツ……いや、ブレザーのようなものを着て、なぜか白い手袋をつけている。
手には角ばった帽子。
一瞬、警察官かと思ったが、そういう雰囲気でもない。
なんだ、誰なんだ。素性を聞こうと口を開きかけたとき、相手が言った。
「ああ、よかった。お留守かと思いました。もう私、困ってしまって」
「……あの、部屋、間違えてませんか?」
今更のように頭痛がしてくる。体を巡る血がドロドロしている。
二日酔いだ。早く中に戻って横になりたい。
「え? 崎野さんですよね」
「……え?」
「あの、私、タクシーの運転手です。大貫さんが下でお待ちです。すみませんけど、来てもらえますか」
「はい?」
いったい何を言っているのだ。
だが、大貫さん、という言葉が頭の何処かに引っかかる。
――大貫さん。そうだ。昨日の夜に確か――
「じゃあ、待ってますからね。あの人、ちょっと変ですよ、困ってるんですから」
そう言って運転手はそそくさと廊下を駆けていった。
着古したポロシャツにしわだらけのチノパン、ボサボサの髪。
まったく自分が嫌になる。なぜこんな理不尽につきあおうとしているのか。
いきなりやってきたタクシー運転手など、無視してしまえばいいではないか。
だが俺はそれができない。
洗面所で手を濡らし、即席の寝癖直しをして、一応サイフと携帯を持ち、部屋を出る。
廊下を進み、階段を降り始めると、確かに一台のタクシーが停車しているのが見えた。
5月の朝8時である。
天気もよく、気持ちの良い春の朝なのだろうが、二日酔いとこの妙な状況のせいですこぶる気分が悪い。
「なんなんだよ……」
誰に言うでもなく呟きながら、降りていく。
やがてタクシーの後部座席の窓が滑らかに開いた。
「やっと来たか。男のくせに準備が遅ぇよ」
大貫だった。確かに昨日の夜、自動販売機の前で会った老人だ。
助けてもらっているくせにひどく偉そうで、感謝の言葉ひとつもなく帰っていった、あのクチの悪い爺さん。

「……どういうことなんです、これ」
「足を痛めたと言ったろうが。こんな爺ひとりじゃ、何もできん。あんた、今日は仕事は休みなんだろ?」
……そういえば昨日、そんなようなことを言った覚えがある。
次の就職先も決まっていない、有給消化中の身であることを恥じるあまり、
土日休みだと言い返したのだ。
「休みだから、なんだって言うんです」
「まあ、いいから乗れ。話は走りながらする」
運転手は、さすが運転手と言うべきか、ここに住んでもう5年以上経つ俺でも知らない裏道をスイスイと進んでいき、やがて大通りに出た。
土曜の朝だからか、道を行く車はあまり多くない。
道沿いに並んだ飲食店もまだOPEN前だ。
保育園の園児だろうか、大きなカートに満載された子供たちの笑顔が見える。
「あの……それで、どこに行くんです」
二日酔いの頭痛に耐えながら聞くと、「どこにって、病院だ」と大貫は答えた。
「病院……ああ」
微かな納得感があった。
大貫は昨日、足を痛めたせいで階段を登れず、それで俺に声をかけたのだ。病院が開く朝を待っていたということなのだろう。
「付き添い……ってことですか」
「そうだ。階段の上り下りくらいならいいが、病院の中まで運転手に介助させるわけにはいかんだろ」
そういうことかと思う。
大貫は先ほど、呼び出したタクシーの運転手に肩を借りて階段を降りたのだろう。
この性格だ、もしかしたら病院内での介助も要求したのかも知れない。
それで断られて、俺の名前を出した。
なんとなく流れは想像できたが、だからといって納得できるはずもない。
なぜ俺ならOKだと思うのか。同じアパートに住んでいる間柄だと言っても、言葉を交わしたのは昨日が初めてなのだ。
……だが、そういった文句は頭の中に浮かぶだけで、声には出ない。
本当に意気地のない人間だ。頼まれたら嫌だと言えず、だから上司にも客にも、そして後輩にすら舐められる。
「どんな仕事をしているんだ?」
俺が黙っていると、どこか真剣な口調で大貫が言った。
「……どんなって、別に普通の営業です。求人広告の」
「求人広告の……そうか」
一体何なのだ、この老人は。
俺のことをなぜ嗅ぎ回る。苛立ちというより不気味さを覚える。
これ以上の詮索をシャットアウトするつもりで、言った。
「でも、辞めるんです。今は有給消化中で、1ヶ月後には退職です」
「なんだと?……どうして辞めるんだ」
驚きのこもった返事。別に関係ないじゃないか、と思う。
俺が会社を辞めようが、別にあんたには何の関係もない。
「どうしてって……まあ、そろそろ次のステップに、というか」
何が次のステップだ。何も決まってなどいない。
なんとなくフリーランスの営業として、と考えていたが、後輩に「そんなに甘くない」と喝破されてしまう程度の思いつきに過ぎない。
本来なら必死に転職活動をしなければならないのだろうが、なぜかそれにも気が向かない。
「あと1ヶ月か……」
大貫が呟くように言ったとき、タクシーは病院に到着した。
「足を痛めたと言ったろうが。こんな爺ひとりじゃ、何もできん。あんた、今日は仕事は休みなんだろ?」
……そういえば昨日、そんなようなことを言った覚えがある。
次の就職先も決まっていない、有給消化中の身であることを恥じるあまり、
土日休みだと言い返したのだ。
「休みだから、なんだって言うんです」
「まあ、いいから乗れ。話は走りながらする」
運転手は、さすが運転手と言うべきか、ここに住んでもう5年以上経つ俺でも知らない裏道をスイスイと進んでいき、やがて大通りに出た。
土曜の朝だからか、道を行く車はあまり多くない。
道沿いに並んだ飲食店もまだOPEN前だ。
保育園の園児だろうか、大きなカートに満載された子供たちの笑顔が見える。
「あの……それで、どこに行くんです」
二日酔いの頭痛に耐えながら聞くと、「どこにって、病院だ」と大貫は答えた。
「病院……ああ」
微かな納得感があった。
大貫は昨日、足を痛めたせいで階段を登れず、それで俺に声をかけたのだ。病院が開く朝を待っていたということなのだろう。
「付き添い……ってことですか」
「そうだ。階段の上り下りくらいならいいが、病院の中まで運転手に介助させるわけにはいかんだろ」
そういうことかと思う。
大貫は先ほど、呼び出したタクシーの運転手に肩を借りて階段を降りたのだろう。
この性格だ、もしかしたら病院内での介助も要求したのかも知れない。
それで断られて、俺の名前を出した。
なんとなく流れは想像できたが、だからといって納得できるはずもない。
なぜ俺ならOKだと思うのか。同じアパートに住んでいる間柄だと言っても、言葉を交わしたのは昨日が初めてなのだ。
……だが、そういった文句は頭の中に浮かぶだけで、声には出ない。
本当に意気地のない人間だ。頼まれたら嫌だと言えず、だから上司にも客にも、そして後輩にすら舐められる。
「どんな仕事をしているんだ?」
俺が黙っていると、どこか真剣な口調で大貫が言った。
「……どんなって、別に普通の営業です。求人広告の」
「求人広告の……そうか」
一体何なのだ、この老人は。
俺のことをなぜ嗅ぎ回る。苛立ちというより不気味さを覚える。
これ以上の詮索をシャットアウトするつもりで、言った。
「でも、辞めるんです。今は有給消化中で、1ヶ月後には退職です」
「なんだと?……どうして辞めるんだ」
驚きのこもった返事。別に関係ないじゃないか、と思う。
俺が会社を辞めようが、別にあんたには何の関係もない。
「どうしてって……まあ、そろそろ次のステップに、というか」
何が次のステップだ。何も決まってなどいない。
なんとなくフリーランスの営業として、と考えていたが、後輩に「そんなに甘くない」と喝破されてしまう程度の思いつきに過ぎない。
本来なら必死に転職活動をしなければならないのだろうが、なぜかそれにも気が向かない。
「あと1ヶ月か……」
大貫が呟くように言ったとき、タクシーは病院に到着した。

俺は何をやっているのだろうか。大貫がいま中にいる診察室の扉を見ながら考える。
タクシーを降りた後、大貫を支えながら病院に入った。
それなりの規模の総合病院だ。確かに足を痛めた老人一人では、指示された窓口に移動するだけでも大変だったろう。
だが、だからと言って俺がついてこなければならない理由はない。
……そうは言っても、既にここまで来てしまっているのだから、何を言っても仕方ないのだが。
10分ほどして扉が開き、大貫が出てきた。
その手には松葉杖があった。病院から借りたのだろう。
おかげで、介助がなくても何とか歩くことができるようだ。
「おう、待たせたな」
おや、と思った。明るい声とは裏腹に、大貫の表情がどこか暗かったからだ。
顔色も悪い気がする。
「じゃ、帰るか」
「あの……足、どうだったんですか」
思わず聞いた。大貫はそのシワの浮いた顔を歪ませて「なんだって?」と言う。
「いや、だから、足。大丈夫だったんですか?」
「阿呆、足じゃない」
「え?」
「足はついでに見てもらっただけだ。ちょっと挫いただけだから、これはスグ治るってよ。俺がここに来たのは、肝臓を見てもらうためだ」
「……肝臓」
そして俺は今更のように、ここが内科のセクションだということに気づく。
大貫はそして小さくため息をつき、言った。
「数値が思ったより悪かった。ついにドクターストップだ。仕事を辞めて休養しろだとよ」
思わずツバを飲み込んだ。ドクターストップ。仕事を、辞める。
「……そんなに悪いんですか」
60代後半、いや、70代か。大貫は老人には違いないが、
それほど深刻な病気を患っているようには見えなかった。
口も悪いし、加えて、人使いも荒い。
もう少し大人しくしてもいいだろうと思うような爺さんなのだ。
「だましだましやってきたんだがな……さすがにもう、毎日職場に行ってフルタイムで働くのは辞めてくれと。徐々にでもいいから休む時間を増やせと言われた」
吐き捨てるように言って大貫は背後の扉を振り返る。
「……簡単に言いやがってよ。そうできねえから続けてるんだっての」
「仕事……何されてるんですか」
俺が聞くと、「ギロチンさ」と大貫は答えた。
「はい?」
「だから、ギロチンだよ。俺はギロチンの設計士だ」
「……」
この期に及んでからかっているのだろうか。俺はそれ以上聞く気にならず、「そうですか」とだけ言った。
タクシーを降りた後、大貫を支えながら病院に入った。
それなりの規模の総合病院だ。確かに足を痛めた老人一人では、指示された窓口に移動するだけでも大変だったろう。
だが、だからと言って俺がついてこなければならない理由はない。
……そうは言っても、既にここまで来てしまっているのだから、何を言っても仕方ないのだが。
10分ほどして扉が開き、大貫が出てきた。
その手には松葉杖があった。病院から借りたのだろう。
おかげで、介助がなくても何とか歩くことができるようだ。
「おう、待たせたな」
おや、と思った。明るい声とは裏腹に、大貫の表情がどこか暗かったからだ。
顔色も悪い気がする。
「じゃ、帰るか」
「あの……足、どうだったんですか」
思わず聞いた。大貫はそのシワの浮いた顔を歪ませて「なんだって?」と言う。
「いや、だから、足。大丈夫だったんですか?」
「阿呆、足じゃない」
「え?」
「足はついでに見てもらっただけだ。ちょっと挫いただけだから、これはスグ治るってよ。俺がここに来たのは、肝臓を見てもらうためだ」
「……肝臓」
そして俺は今更のように、ここが内科のセクションだということに気づく。
大貫はそして小さくため息をつき、言った。
「数値が思ったより悪かった。ついにドクターストップだ。仕事を辞めて休養しろだとよ」
思わずツバを飲み込んだ。ドクターストップ。仕事を、辞める。
「……そんなに悪いんですか」
60代後半、いや、70代か。大貫は老人には違いないが、
それほど深刻な病気を患っているようには見えなかった。
口も悪いし、加えて、人使いも荒い。
もう少し大人しくしてもいいだろうと思うような爺さんなのだ。
「だましだましやってきたんだがな……さすがにもう、毎日職場に行ってフルタイムで働くのは辞めてくれと。徐々にでもいいから休む時間を増やせと言われた」
吐き捨てるように言って大貫は背後の扉を振り返る。
「……簡単に言いやがってよ。そうできねえから続けてるんだっての」
「仕事……何されてるんですか」
俺が聞くと、「ギロチンさ」と大貫は答えた。
「はい?」
「だから、ギロチンだよ。俺はギロチンの設計士だ」
「……」
この期に及んでからかっているのだろうか。俺はそれ以上聞く気にならず、「そうですか」とだけ言った。
短編小説 愛のギロチン(全3回)

作:児玉達郎
愛知県出身、千葉県在住。2004年、リクルート系の広告代理店に入社し、主に求人広告の制作マンとしてキャリアをスタート。取材・撮影・企画・デザイン・ライティングまですべて一人で行うという特殊な環境で10数年勤務。
求人広告をメインに、Webサイト、パンフレット、名刺、ロゴデザインなど幅広いクリエイティブを担当する。
2017年7月フリーランスとしての活動を開始。インディーズ小説家・児玉郎としても活動中(2016年、『輪廻の月』で横溝正史ミステリ大賞最終審査ノミネート、2017年『雌梟の憂鬱』で新潮ミステリー大賞予選通過)。BFI(株式会社ブランドファーマーズ・インク)のスペシャルエージェント。
愛知県出身、千葉県在住。2004年、リクルート系の広告代理店に入社し、主に求人広告の制作マンとしてキャリアをスタート。取材・撮影・企画・デザイン・ライティングまですべて一人で行うという特殊な環境で10数年勤務。
求人広告をメインに、Webサイト、パンフレット、名刺、ロゴデザインなど幅広いクリエイティブを担当する。
2017年7月フリーランスとしての活動を開始。インディーズ小説家・児玉郎としても活動中(2016年、『輪廻の月』で横溝正史ミステリ大賞最終審査ノミネート、2017年『雌梟の憂鬱』で新潮ミステリー大賞予選通過)。BFI(株式会社ブランドファーマーズ・インク)のスペシャルエージェント。
関連記事
ちょくルートMagazineについて
ちょくルートMagazineは、経営戦略は「人」であると考える経営者、人事担当者向けに人材不足の問題を解消すべく、採用に関するニュースや求職者動向、成功事例を発信するメディアです。特に、自社採用サイトを活用した採用手法をお届けしています。