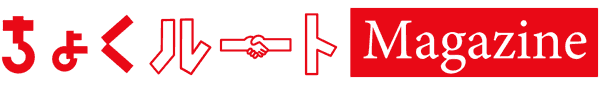愛のギロチン ~Part2「採用ってもっと人間的なことじゃないの?」

退社までに引継ぎで同行する後輩に、求人業界への想いを聞いて違和感を感じる。
後輩の求人に対する思いが、自分と全く違うのだ。
自分は少なくても、この仕事が好きだったはずだ。
何かに気づき始めた「俺」が最後にすることになった仕事とは・・

週明けの月曜日、俺は久々に会社に行った。
有給消化中ではあるのだが、まだいくつかの引き継ぎ業務が残っているので、こうして時々は出勤する必要があるのだ。
取引先の一つに新任の営業マンと引き継ぎの挨拶に行った帰り、花見川沿いの田舎道を駅に向かって歩いていた。
「それで先輩、辞めた後はどうされるんですか?」
3年前の新卒で入社してきた若い営業マンが聞いてくる。
まだ年齢は24か25くらいだろう。その童顔は社会人と言うより大学生、
いや、場合によっては高校生のようにも見える。
だが、今の女性はこういう童顔が好きなのか、社内の女子社員からはひどく人気があるのだと聞いた。
確かに背も高いし、こういうのを清潔感というのだろうか、ファッション雑誌に載っていてもおかしくないような爽やかさがある。
それにそもそも、こいつは先月、若手ランキングの中でトップの成績を収めた営業マンだ。
「いや……まだハッキリとは決めてないんだがな。じっくり考えようと思ってる」
こんな若者にまで虚勢を張る元気はなかった。40間近の自分とは住む世界が違うのだ。
すると彼は意外なことを言った。
「まあ、確かに求人系ってもう微妙ですもんねえ。辞めて正解ですよ、先輩」
「え?」
俺は驚いてしまった。一回り以上年下の新人の言葉だとは思えなかった。
「……微妙って、なにが」
「なんていうか、僕もまだこの仕事3年位ですけど、あんまり面白くないっていうか」
「面白くない」
「ええ。だってこんなの、単なる枠(わく)売りじゃないですか。このサイズならいくらですよ、オプションつけたらいくらですよ、ってやってるだけ。採用マッチングだなんて偉そうに言ってますけど、そのマッチングの仕組みを作ってるのは僕らじゃなくて版元なわけだし。僕らはただその間でちょこちょこ動いて手数料を稼いでるだけです」
思いのほか辛辣な言い方に驚く。
後輩はその子供のような顔を歪め、どこか自嘲的に言い添えた。
「正直、僕も長く留まるつもりはないですよ。営業マンとしてのスキルがもう少し上がったら、さっさと別の業界に行くつもりです」
「……そうか」
後輩はそして、なぜか懐っこい笑顔を見せた。
「先輩がどんな業界に行くかはわかりませんけど、こんな業界オサラバして当然ですよ。僕もそのうち後を追いますから」
駅に到着すると、錦糸町にあるオフィスに戻るという後輩と別れて、千葉方面の電車に乗った。
後輩に言われた言葉が頭の中に残っている。
単なる枠売り。確かに、そういう側面はあるだろう。
俺たちが採用マッチングの仕組みを作ったわけでないのも事実だ。
俺たちは版元が作った巨大なメディアの傘の下で、多少の手数料をひっかき集めてなんとか生きながらえている。
だが、と思う。
求人広告の営業という仕事。それはそんなに価値のない仕事なのだろうか。
……俺はそうは思わない。いや、少なくともそうは思ってこなかった。
価値の有無はよくわからない。
でも、俺はあの後輩が言うほど、この仕事が嫌いではなかったのだ。
確かに、単純な仕事だとは思う。
求人のニーズがあるお客さんを訪ね、募集職種や労働条件を聞き、それを原稿にして掲載する。
それだけだ。
数万円の契約を必死で取りつけ、そのほんの2〜3割の手数料を利益として手に入れる。
もちろんそれは会社に入る利益であって、そのまま自分のインセンティブになるわけではないし、
そもそも俺は会社の定めた目標金額にすら届かない週も多かったのだが、
それでも俺はこの仕事を15年以上も続けてきたのだ。
単なる枠売り? 手数料をかすめるだけの仕事?
そんなことはない。
そんなことは……
しかし、それならどう違うのか、という問いに明確な答えは出てこない。
モヤモヤした気分のまま稲毛駅を降り、いつものコンビニで晩飯用の弁当と惣菜をいくつか購入して、家に向かった。
まだ夕方の四時だったが、一人の晩飯のために外に出る元気もなかった。
アパートの前に到着し、ため息混じりに階段を登ろうとしたとき、上から声がした。
「おう、営業マン。待ってたぞ」
顔をあげると、大貫がいた。

「本当に大丈夫なんですか? 肝臓が悪いんでしょ」
「うるせえな。居酒屋に来て烏龍茶なんて飲めるかよ」
居酒屋を選んだのは自分じゃないか、と思いながら、
キリンビールのロゴが書かれた小さなグラスにビールを注いだ。
「さあ、お前も飲めよ」
「……いただきます」
今度は大貫が俺のグラスへ。溜まっていく黄金色の液体を見ながら、
どうしてこんなことになっているのかと考える。
三十分ほど前、家に戻ってきた俺を大貫が待ち受けていた。
そして、顔を見るなり「ちょっくら飲みに行こう」と言ったのだ。
そのとき俺の手には、買ったばかりのコンビニ弁当と惣菜があった。
断るのが苦手な俺だって、これほど明確な理由があれば、言えたはずだった。
すみません、晩飯買ってきちゃって、だからつきあえません。
だが俺は断れなかった。いや、あるいは、断らなかったのかもしれない。
後輩に言われた言葉に心がざわついていた。
まるで俺の15年を否定するような言葉。
いやそれ以上に俺は、求人事業そのものを否定されたことに動揺していた。
そんな時に俺は大貫に誘われたのだ。
「どうした、グイッと行けよ」
「はあ」
言われるままにグラスを煽った。冷たくて苦い液体が喉を駆け下りていく。
気がついたときにはグラスは空になっていた。
「おっ、景気がいいじゃねえか。じゃ、俺も」
そう言って大貫も同じように一気に飲み干し、
すぐに次の一杯を注いでくる。本当に肝臓は大丈夫なのだろうか。
「大貫さんって、一人暮らしですよね」
「ん? ああ、そうだ」
「ご家族とか……お子さんとかは」
言った途端、大貫の表情がこわばった。
「なんでそんなこと言わなきゃなんねんだよ」
強い口調に思わず言葉をつぐんだ。視線を落とし、黙る。
何か事情があるのかもしれない。だが、それにしたって、そんなに怒ることはないではないか。

「……なんですか」
今度はなんだ。どうせまた、何かの手伝いをさせられるのだろう。
どこまで図々しいのだ。この爺さんは。
だが、続く言葉は意外なものだった。
「あんた、求人の営業マンだって言ってたよな」
「え? ……ええ、まあ、もうすぐ辞めますけど」
「求人広告を扱ってるってことだな?」
「そうですけど。……それが何か」
大貫は小さくため息をつき、グラスを口に運ぶ。
ゆっくりとビールを空にして、言った。
「あんた、うちの求人やってくんねえかな」
「……はい?」
「言ったろ、俺はそろそろ仕事を辞めなきゃなんねえ」
「ああ、はい」
「でもうちの会社は、俺が辞めたら困るんだ。俺と同じ仕事ができる人間がいねえんだよ」
「……でも、何度も言っているように私はもう退職が決まっていて」
「まだ籍はあんだろうがよ」
「それはそうですが……もしあれなら、ウチの営業マンを紹介しますよ」
言いながら、自嘲的な気分になった。
そうだ。仮に大貫が本気だとしても、厄介者扱いされている俺が担当する必要はない。
もっと優秀な、そう、例えば今日引き継ぎアポに行ったあの若手営業のような人間に任せた方が、
いい結果が出る。
15年のキャリアを持つ自分より、あの新人の方が。
苦笑いを浮かべて言った俺を、大貫は真剣な表情で見つめた。
「お前……採用をなんだと思ってやがる」
「……え?」
「俺は、どこの馬の骨ともわからねえ奴に、大事な採用を任せる気にはなんねえよ」
ドキリとした。
何かいま、重要な何かが目の前を通り過ぎた気がする。
「いいかい、崎野さんよ。俺はあんたの会社じゃなく、あんたに頼んでんだ。
やるのかやんねえのか、決めるのはあんただろうが」
「……」
すぐには答えられなかった。
そもそも、会社側がなんと言うかわからない。
いや……そうではない。俺は自信がないのだ。
大貫の想いに応えられる自信が……。
だが一方で、警笛のようなものが自分の中で鳴っているのを感じた。
今ここで逃げたら、本当に自分がダメになってしまうという、よくわからない恐怖。
それに、大貫の言葉だ。
採用を何だと思ってやがる。
そうだ、俺は今日、あの後輩にそう言いたかったのではないか。
まるで心の通っていないあの言葉を、そう怒鳴りつけてやりたかったのではないのか。
「まあ……急に言われてもな、あんたも答えづらいのかもしれ……」
「やります」
気がついたら言っていた。
「あん?」
「やらせてください」
大貫がニヤリと笑い、そして、瓶ビールを俺に向かって傾けてきた。

「え?」
俺はグラスでビールを受けながら答える。
「いやな、あんたは覚えてねえだろうが……」
そして大貫は、もう何年も前、俺がアパートの下で電話している姿を見たのだと言った。
「携帯電話持ってよ、何度も謝ってた。
ああ、こいつ、お世辞にもうまい営業じゃねえんだなって思った」
「……大きなお世話ですよ」
「まあ聞けよ。とにかくあんたは何度も何度も謝ってた。
何をしでかしたのかなんて知らねえけどさ。で、最後にこう言ったんだよ」
大貫は手を耳に当て、その時の俺を真似るように言った。
「でも、採用って、そんな数字合わせみたいなものなんですか。
もっと、人間的なものなんじゃないんですか」
「……」
「ま、堂々と言うって感じじゃなかったけどなあ。
ボソボソって、不貞腐れてるみたいな感じだったけど」
そんなことを自分が言ったのか。
記憶を探ったが思い出せなかった。
だが、大貫がそう言うのなら事実なのかもしれない。
「……確かに言ったのかもしれませんけど、それがどうしたんですか」
俺が、それこそ不貞腐れたように言うと、大貫はわははと笑った。
「不器用だが、まあ、こういう野郎の方が信用できるとは思ったな」
褒められているのかけなされているのか。
だが俺は、自分の心がどこか軽くなっていることに気づいていた。
注がれたビールを再度あおり、自分で瓶を手にしてすぐに次を注いだ。
「まあ、とにかく、やらせてもらいますけど、それにはいろいろ教えてもらわないと。
そもそも大貫さんのお仕事って何なんですか」
「こないだ言ったじゃねえか」
こないだ? ああ、確かに病院で何か言っていた気がするが、明らかに冗談だったではないか。
「いや、あれはだって……」
「ギロチンだよ」
そう言って大貫はドン、とグラスを机に置くと、胸を張った。
「俺はギロチンの設計士だ」

「ギロチン」の意味はやがて知れた。
ギロチンと言えば、フランス革命などで使われた断頭台が思い浮かぶが、
世の中には「工業用ギロチン」と呼ばれる機械があり、
金属やプラスチックなどの資源を切断するのに使われているらしい。
大貫が言っていたのはその、工業用ギロチンのことだった。
居酒屋で飲んだ次の日、俺は上司に新規案件担当の了解を取った。
有給消化中になんで、と最初は怪訝そうだったが、知り合いから頼まれたと説明すると、あっさりと許可がおりた。
まあ、会社としては特にデメリットはないのだから当然とも言える。
そしてさらに数日後、俺は大貫の職場だという「多賀岡工業」にやってきた。
どこか照れたような表情で俺を迎えた大貫は、その小さな町工場風の会社を案内してくれた。
予想通りと言うべきか、多賀岡工業は郊外にある小さな会社だった。
いわゆる家族経営的な体制だが、社長の多賀岡昭一はまだ三十代半ばで、創業社長である先代の息子、つまり二代目らしい。
先代は数年前に急逝し、息子の昭一が跡を継いだとのことだ。
「先代の多賀岡八十吉(やそきち)てのとは、ガキの頃からのつきあいでよ」
大貫はそう言って笑い、一緒についてきていた昭一の肩をバンと叩く。
「このガキはよ、生まれたその日に俺の顔に小便ひっかけやがったんだぜ。こりゃ大物になるって言われたが、結局はこんな寂れた町工場の社長だ。情けなくて涙がちょちょ切れらあ」
昭一は小柄で大人しそうな男だったが、大貫の憎まれ口をニコニコして聞いている。
「大貫さんは、いつもこんな感じですか?」
俺が聞くと、ええ、と笑顔でうなずく。
「まあ口が悪いんで、困ってますよ。お客さんがお見えの際は倉庫に閉じ込めておくんです」
「何だとコラ昭一、言わせておきゃあこのガキが」
横で吠える大貫にも昭一は顔色一つ変えない。
意外と肝が座っているのかもしれないと思ったが、どうやら違った。
「まあでも、この人のうるさい文句が聞こえないと、なんかどうも調子が出ないんですよねえ。僕なんてほら、生まれたときからずっと聞いてるわけだから」
要するに、それくらい多賀岡家と大貫は古い関係なのだろう。
そして、このやり取りを見ていた他の社員たちも、みな笑っている。
明らかに大貫はこの職場で好かれているようだった。

「事業としては、どんなことを?」
昭一は「そうですねえ」と少し考えて答えた。
「わかりやすい言葉で言えば、リサイクル関係です。リサイクルの工程で使う機械を作って、売っています。廃プラ梱包機、金属圧縮機、破砕機とか、いろいろ」
「大貫さんは、工業用ギロチンの設計をされているわけですね」
「ええ。ギロチンだけでなく、多賀岡工業オリジナルの機械のほとんどの設計に関わってもらってます」
「他に設計の仕事に就いている方は?」
「いないんですよ。過去にはいたんですが、体調を崩したり別の仕事に転職したりして、いなくなってしまって。ここ3年ほどはもう大貫さん一人に頼りっぱなしで」
なるほどと思う。だから大貫は辞められないのだ。
こういう専門的な知識が必要な仕事は、採用難易度も当然高い。
まして多賀岡工業のような、お世辞にも有名企業は言えない会社では、なおさらだろう。
「どういう人なら、大貫さんの後を継げるんでしょう」
そう聞くと、「どんな人がいいでしょうね」と昭一が大貫に聞く。
「どんな人ってお前、根性があって真面目で男気のあるやつなら、誰だっていいよ」
「技術的な経験はなくても大丈夫なんですか」
大貫は顔を歪め「んなもんいるか」と吐き捨てる。
「俺が本気で教えりゃ、どんな奴だろうが半年で一人前だ。舐めんじゃねえよ」
と、昭一が俺の耳元でこっそり言う。
「こういう指導に半年耐えれるか、ってのが問題なんです」
「ああ……」
「なんだとこの野郎、そんな腰抜け野郎はこっちから願い下げだ!」
聞こえていたらしい。
その時、大貫が別の社員に呼ばれて席を外した。
昭一はそんな大貫を嬉しそうに見つめ、「まあ、でも実際、そうなんです」と続ける。
「やっぱり、大貫さんのやってらっしゃる仕事は、1日2日でマスターできるようなものじゃないんですよ。
設計の中でも特殊な分野ではありますし、それに、なんというか、知識だけじゃなくてカンのようなものが重要になってくる世界でしてね。
実はこれまでも何度か採用に挑戦したんですが、なかなかうまくいかなくて」
「あ……そうだったんですか」
「ええ。採用できてもすぐ辞めてしまったり、そもそも応募が来なかったり。
だから今回はラストチャンスなんです。これでダメなら、もう今後は設計自体を外注するしかない」
「ラストチャンス」
「大貫さんの体調を考えれば、むしろこうなる前にその決断をすべきだったんでしょうけどね。
ただ、大貫さん自身が、後釜を育てるまでは絶対に辞めないと譲らないものですから。
……あの人、口は悪いですけど、本当に優しい人なんです」
「優しい?」
思わず聞くと、昭一はさらに笑顔を深くした。
「ええ。そのあたりが求職者の皆さんにも伝わるといいんですけどね」

愛知県出身、千葉県在住。2004年、リクルート系の広告代理店に入社し、主に求人広告の制作マンとしてキャリアをスタート。取材・撮影・企画・デザイン・ライティングまですべて一人で行うという特殊な環境で10数年勤務。
求人広告をメインに、Webサイト、パンフレット、名刺、ロゴデザインなど幅広いクリエイティブを担当する。
2017年7月フリーランスとしての活動を開始。インディーズ小説家・児玉郎としても活動中(2016年、『輪廻の月』で横溝正史ミステリ大賞最終審査ノミネート、2017年『雌梟の憂鬱』で新潮ミステリー大賞予選通過)。BFI(株式会社ブランドファーマーズ・インク)のスペシャルエージェント。
関連記事
ちょくルートMagazineについて
ちょくルートMagazineは、経営戦略は「人」であると考える経営者、人事担当者向けに人材不足の問題を解消すべく、採用に関するニュースや求職者動向、成功事例を発信するメディアです。特に、自社採用サイトを活用した採用手法をお届けしています。